
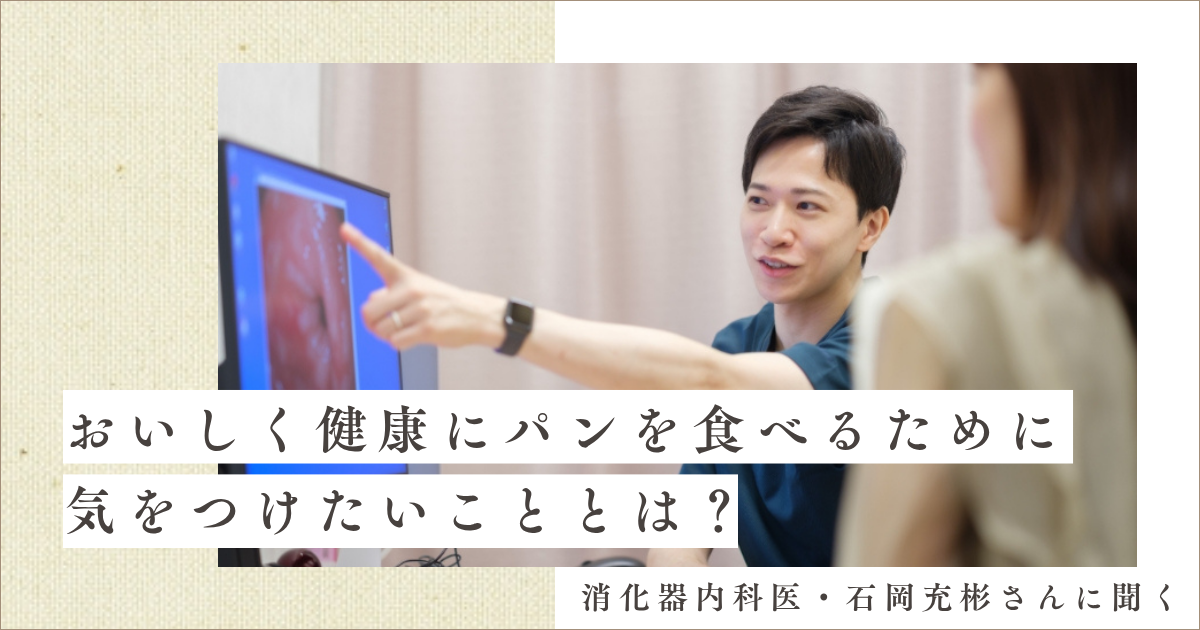
消化器内科医・石岡充彬さんに聞く、おいしく健康にパンを食べるために気をつけたいこととは?

日々のパン活を楽しむなかで、「ついパンを食べ過ぎてしまう」など、お悩みを持つパン好きさんも多いのではないでしょうか。
そこで今回、日本橋人形町消化器・内視鏡クリニックの院長で消化器内科医の石岡充彬さんに、おいしく健康にパンを食べ続けるために知っておきたいポイントをお伺いしました。
石岡充彬さん(医師/日本橋人形町消化器・内視鏡クリニック院長)

1986年生まれ、秋田県育ち。秋田大学で消化器内科全般を経験し、各種専門医資格および医学博士号を取得。2018年よりがん研有明病院にて、内視鏡診療に特化した知識と経験を積む。都内最大手内視鏡クリニック院長職を経て、2024年7月に「日本橋人形町消化器・内視鏡クリニック」を開院。
2021年より、Instagramアカウント「東京パン生活。(@tokyo_pan.life)」にて東京都内のおいしいパンの紹介をスタート。フォロワー数2万人を超える(2025年11月現在)。2025年10月には、新宿NEWoManの「パンまつり」でコラボパンを販売。現在、クリニック近隣にパンメニューを提供するカフェを準備中。
──さっそくですが、「パン(小麦)は消化が悪い」といった情報を目にしたことがあり、パン好きとしては気になります。石岡さんは消化器内科医として働きながら、Instagramでパン紹介をしているパン好きさんでもありますが、どのように考えておられますか。
医療の世界ではここ数年、「グルテン=悪者」というイメージが広まりすぎていると感じています。確かに一部の方にとっては、小麦が腸に負担をかける場合もあります。しかし、すべての人に当てはまる話ではありません。
私たちの腸には“相性”があります。例えば、セリアック病(※)と呼ばれる疾患を持つ方や、小麦アレルギーの方はグルテンを避ける必要がありますが、基本的には好きなものを食べながらでも健康は維持できると私は信じています。その上で、小麦と上手に付き合うために知っておきたい概念があります。
※グルテンに反応して引き起こされる自己免疫疾患のひとつ

2020年には、1年間で「食べログ パン百名店 Tokyo」を全店制覇。多くのパンと出会ううちに「自分だけで楽しむのはもったいない」、「もっとパンの魅力を伝えたい」と思うようになり、Instagramでパンの投稿を始めたのだと言います。
まず、近年注目されているのが「FODMAP(フォドマップ)」です。これは腸内で発酵しやすい糖質の総称で、Fructose(果糖)、Oligosaccharides(オリゴ糖)、Disaccharides(二糖類)、Monosaccharides(単糖類)、Polyols(ポリオール)を指します。
小麦にはこのうちの“フルクタン(オリゴ糖の一種)”が含まれており、腹部膨満感(いわゆるガス腹)を引き起こすことがあります。そのため、FODMAPの観点からは「どんな小麦製品を・どのくらい食べるか」が大切になります。
もうひとつ、SNSなどで「リーキーガット(腸漏れ症候群)」という言葉を目にしたことがあるかもしれません。これは小麦に含まれるグリアジン(グルテンの一部)により、腸の粘膜バリアが一時的に弱まり、通常なら吸収されない物質が体内に入り込む状態を指します。
ただし、「リーキーガット=小麦が原因」という単純な構図ではありません。ベースの腸の状態や腸内細菌バランス、ストレス、睡眠や食生活など複数の要因が関与しているのを理解しておくことが大切です。


──私たちが日頃からパン選びやパンを食べる際にできることはありますか?
パンを選ぶ際に注目したいのは「原材料」と「発酵」です。発酵時間をしっかり取っているパン(天然酵母やルヴァン種など)は、FODMAPが比較的少なく、消化にやさしい傾向があります。ハード系や全粒粉、ライ麦入りのパンは食物繊維も豊富で、腸内環境を整える上でもプラスです。
一方で、砂糖や油脂、乳製品が多く使われた菓子パンや総菜パンはFODMAPが高くなりやすく、敏感な方では不調の原因になることも。嗜好品として時々楽しむ程度にするのがおすすめです。
私は消化器内科医として、またパンを愛する一人として、「食べない」という極端な選択ではなく、「上手に食べながら体調を整える」ことを大切にしています。パンを選ぶときに素材や発酵方法を意識し、自身の許容量を知り、その範囲内で楽しむことが賢い食べ方だと思います。
──「つい食べ過ぎてしまう」のを防ぐために、気を付けたいポイントを教えてください。
パンは満腹感を感じるまでに少し時間がかかる食べ物です。ごはんに比べて早喰いをしてしまいがちなのですが、これが食べすぎの原因になることがあります。そのため、パンを食べるときはよく噛んで、時間をかけてゆっくり食べることが大切です。
ハード系のパンやクラストのしっかりしたパンは、自然と咀嚼回数が増えるため、満腹中枢が刺激され、食べすぎを防ぎやすくなります。
また、パンを単体で食べるのではなく、野菜・発酵食品・たんぱく質・水分を組み合わせることもポイントです。食物繊維を含むサラダやスープ、発酵食品のヨーグルトやチーズを添えると、血糖値の上昇がゆるやかになり、腸にもやさしい食事になります。
──今日から実践できそうです。最後に、ぱんてな読者へメッセージをお願いします。
健康の基本は“我慢”ではなく“自分の体への理解”です。単純に小麦やパンを悪者と捉えるのではなく、自分の体と相談しながら選ぶことで、心にも体にも優しい食生活を送ることができます。
パンは私にとって、単なる食事ではなく“生活の喜び”です。だからこそ、同じパン好きの皆さんには「我慢ではなく、上手に付き合う」方法を知っていただきたいと思います。
パンの香ばしさ、小麦の甘みや旨み。それを安心して味わえるように、私も医師としての知識とパン愛の両面からサポートしていきたいと思っています。

「Pain des Philosophes(パン・デ・フィロゾフ)」の「アサマ山食パン」。 「『アサマ山食パン』は、パンにのめり込むきっかけになった、言わば“人生を変えてくれたパン”。これを食べると、パンを愛し始めた原点に立ち返ることができます」と石岡さん。

